“現場百遍”で挑む「輸配送最適化」:現場の「正しい非合理性」もテクノロジーで支える
輸配送最適化ソリューションを手掛けるオプティマインドは、独自の組合せ最適化アルゴリズムを活用した『Loogia(ルージア)』を起点にTMS領域へと展開を進めています。お客様が抱える課題や『Loogia』の特徴、業界の今後の展望などについて、松下健氏(代表取締役社長)にお話を伺いました。

株式会社オプティマインド
名古屋大学発のITベンチャーとして2015年設立。「新しい世界を技術で創る」をミッションに掲げ、独自の組合せ最適化技術と実走行データ解析を活用した自動配車システム「Loogia配車作成」をコアとし、物流ネットワークの可視化/再編、拠点の配置戦略の策定支援などお客様の輸配送最適化を実現するために幅広いソリューションを展開している。
代表取締役社長 松下 健 氏 Ken Matsushita
岐阜県岐阜市出身。名古屋大学情報文化学部を卒業し、同大学大学院情報学研究科数理情報学専攻博士後期課程を単位取得満期退学し、現在は同大学大学院情報学研究科招へい教員。2015年にオプティマインドを創業。配車DXをアルゴリズムで実現し、物流の持続可能性の向上に挑戦している。
“物流デジタル人材”の重要性
――御社の特徴についてご紹介いただけますか。
組合せ最適化アルゴリズムや機械学習などの高度なIT技術をベースに、自社開発した『Loogia』を中心として、お客様の輸配送の最適化を支援しています。創業からしばらくは「ラストワンマイル」と言われる個人宅への配送ルート最適化に重点を置いて展開していましたが、現在は輸配送業務全体を支援する機能群の提供、店舗配送や幹線輸送、自動車輸送などのBtoB輸送にまで領域を広げています。
輸配送の最適化は、一見簡単そうですが、例えば「このドライバーは今日早退する」「この配送先は14時までに届けなければいけない」など、現場ごとに複雑な要件が数多く存在します。それらを1つ1つ考慮するには、アルゴリズムもその都度開発しなければなりません。創業から10年間、現場に足を運ぶこととアルゴリズム開発への投資に惜しむことなく取り組み、「現場で使える」ソリューションに育ててきたのは、国内では当社だけだと自負しています。
――デジタル化への意識は浸透してきているのでしょうか。
創業した10年前から比べると、かなり変わってきています。お客様と会話をしていても肌で感じるのですが、特に昨年から今年にかけて、あらゆる方々が「DXやIT、AIへ投資をしなければ」と危機感を抱かれています。
以前は「まだまだ使えるものと使えないものがある」「AIはもう少し待とうか」という声が多かったのですが、いよいよ皆さんが「今からどのように取り組んでいくかで数年後の会社の未来は大きく変わる」という危機意識を強く持たれていると感じます。
そうした流れがある一方、お客様の社内における「物流×DX」や「物流×IT」などに一定の知見を持つ「物流デジタル人材」の獲得がもっと必要なのではないか、と私は感じます。CLOや、今後CLOになるであろう方と対話すると、皆さん自社の物流改革に対して素晴らしい構想をお持ちです。しかし、CLOはスーパーマンではありません。プロジェクトとして実際に動く段階になれば、例えば法務のプロや現場のプロ、様々なプロ人材からなる“CLOチーム”が必要となります。
そこに欠かせないのが「物流デジタル人材」です。そういった人材を内製化、もしくは一部外注も含めてチーム編成できる会社とそうではない会社では、5年後の姿は大きく異なると考えています。
――次世代の物流デジタル人材は、どうやって輩出していくとよいとお考えですか。
2つの方法があると思っています。1つは物流畑の人がデジタルを習得するケース、もう1つはデジタル畑の人が物流を習得するケースです。前者の方が人材としては多いでしょう。「以前、物流現場にいたが、デジタル技術に興味がある」という20~30代の人を引き上げ、教育プログラムなどを用意して社内で育成するのが一番の近道です。
他方、IT畑の人に物流の知見を習得してもらうのなら、まずはその人たちを物流市場に引き込むことが必要になります。中途採用でヘッドハンティングする、あるいは専門的に学んだ学生を新卒のタイミングで採用するなどです。そもそも物流業界を知ってもらうことがスタートだと考えており、私も積極的に大学で講演などを行い、学生たちに少しでも物流に関心を持ってもらえるよう努めています。
「物流」と聞いて、最初は宅配便のイメージしかなかった学生も、サプライチェーンとは何か、デジタルによる変革余地がどれだけ大きいかといった話をすると、「私たちが学んだ技術は物流に活かせるのか!」と気付いてくれます。物流に関わる仕事の魅力を学生に発信し続けることが大事だと思っています。

事前シミュレーションで課題の本質的議論も
――輸配送最適化の課題に対しては、どのようなソリューションを提供しているのでしょうか。
『Loogia』の配車最適化に関わるコアな部分のアルゴリズムも強化を続けていますが、冒頭でもご紹介したように、お客様ごとに存在する現場の要件に応じて、例えば基幹システムやWMSとのつなぎ込み、機能の追加開発なども積極的に行っています。
当社の一番の強みは、カスタマイズ力とオペレーション構築力です。お客様の実態に合わせたアルゴリズムの個別アレンジにはかなりの人員と時間を割いており、ノウハウも蓄積されてきました。システム導入後もサービスの改善を続けていますので、環境変化にも速やかに対応することが可能です。
また、システム導入以前の段階として、輸配送最適化に取り組んだ場合の効果や影響を事前にシミュレーションする『データ・アナリティクス・サービス(DAS)』も提供しています。これは、当社のスタッフがCLOや物流部長の方に伴走しながら各種要件や懸念点を丁寧に拾い上げ、様々なパターンでシミュレーションした結果をメリットとデメリットを含めてご提供するものです。
例えば、拠点の配置最適化や配送エリア再編、共同配送におけるインパクト試算などシミュレーションを実施することで、「何がボトルネックなのか。何を変えたら、どれくらい改善インパクトが出るのか」を様々な評価軸から検討できます。先ほどお話しした、CLOを支える物流デジタル人材の役割の一部を、当社が外部から支援するようなイメージです。本質的な課題の議論にご活用いただけるので、お客様からも「効果と影響が可視化されたことで、当初とは別の課題に優先的に取り組んだ方が、良い結果が得られそうだとわかった」「システム投資の決裁を取る際の大きな説得材料になる」とご好評いただいています。
――導入提案にあたって大切にしていることは何でしょうか?
当社では「現場百遍」という言葉を大事にしています。お客様の物流は千差万別です。だからこそ、とにかく現場に入り込み、お客様ごとの現場要件やシステム環境、業務フローなどを徹底的に理解することに注力します。以前、ドライバーアプリの導入支援で当社のエンジニアが、助手席から横にいるドライバーさんに操作の説明をしていたとき、「逆光で画面が暗いとボタンが見づらく、操作に迷う」と言われたそうです。これはまさに、オフィスで机上検証しているだけではわからず、現場に足を運んだから気付けたことです。
また、物流現場には「正しい非合理性」があると思っています。課題解決に向けて合理的になりすぎず、「現場ごとの最適化」を実現するためにテクノロジーの力でご支援したいと考えています。だからこそ私たちはお客様の現場に、積極的に足を運ぶようにしています。
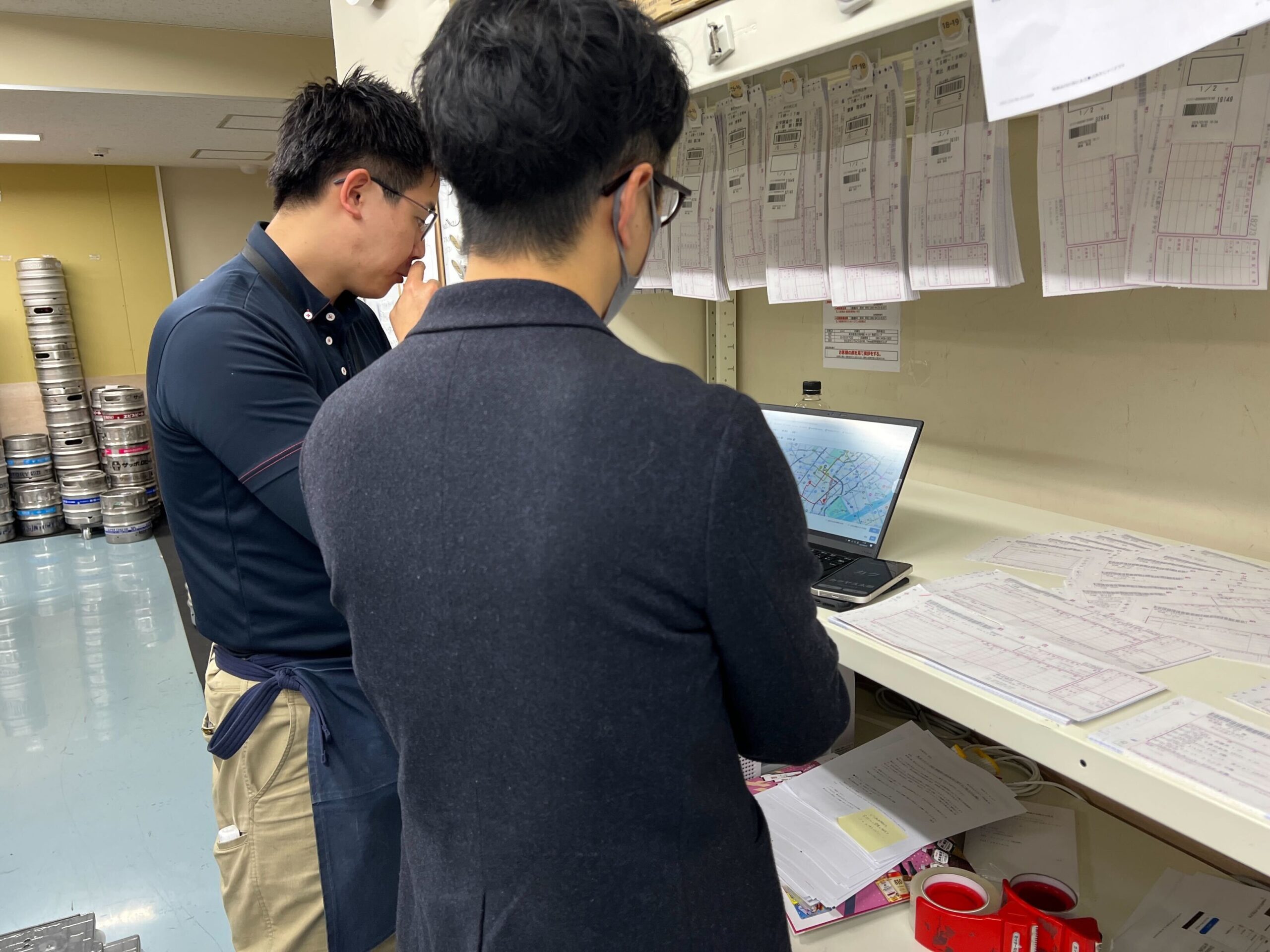
オプティマインドが大切にする「現場百遍」の言葉どおり、メンバーは日々現場に出向き、顧客課題をリアルに把握している
――今回「ロジスティクス強調月間2025」のサポーターに参画いただいた経緯をお聞かせください。
昨年に続き、会社としてはサポーター、個人としても推進委員会の委員で参画させていただくことになりました。当社は「輸配送の最適化」という観点において、業界全体の実情を横串で一番知っているという自負があります。荷主企業や物流会社などの当事者ではない立場だからこそお伝えできることがあると思うのです。
物流・ロジスティクス領域においては、「競争」だけでなく「協調」も大事ですから、強調月間の一環として開催されるイベントなどは、横のつながりを作って改善事例を共有するうえで非常によい機会です。企業同士が正式にアポイントを取って、改善事例について情報交換するのはかなりハードルが高いですよね。しかし、ほぼ公的な場ともいえる日本ロジスティクスシステム協会のイベントなら、立ち話をしながら改善に関するちょっとした情報交換をするなど、気軽に交流できます。話してみると、実は意外な企業同士が同じ課題感を持っていることに気付く、といったケースもあるでしょう。
物流ならではの温かみや価値をデジタル情報に
――ロジスティクスの未来をどのように予測・想像されていますか。
物流は「物だけでなく、想いも運んでいる」と言われますが、そうした現場にある温かみや人間くささを失くしてはいけないと考えています。ドライバーさんがアプリの指示どおりの場所に行って黙って荷物を置いてくるのではなく、例えば「○○さんの家の息子さん、大きくなったね」といった会話が自然に生まれたり、「○○さんの家は、この時間は赤ちゃんが寝ているから静かに行こう」などの配慮がなされていたり、そういうところが物流の良さでもあると思うのです。
少子高齢化が進んだ社会でみんなが幸せになるには、コミュニティでの人と人とのつながりや助け合いが大事になるでしょう。例えば、過疎が進んで全てのお宅に配送できなくなった地域では、公民館に荷物を降ろすと人々が取りにやって来る。お隣さんの荷物を一緒に運んであげる人がいたり、取りに来られない人の家には宅配ロボットで支援したり。そんな、人とテクノロジーがうまく融合した温かい社会を作りたいですね。
――今後に向けた目標をお聞かせください。
ここから先、温かい社会を作りながら、お客様である荷主企業が成長していくためには、属人的な情報をどのようにデジタル情報として蓄積していくかが大事だと考えています。先ほども話したように、荷物の受け手側の事情をつかんでいるのはドライバーさんです。店舗配送で「ランチタイムの納品は、売り上げの邪魔になるので裏の搬入口から」といった情報があっても、そのドライバーさんが体調不良などで休んだ場合、他の人には共有されません。こうした点を改善できれば、働く側にとっても届け先にとっても安心感につながるのではないでしょうか。また、個人宅の配送でも、「小さなお子さんがいる」「ソファの買い替えを検討している」など、ドライバーさんだけが知りえる情報をうまくマーケティングに活用するなど、ナレッジをお客様の利益創出につなげていきたいと考えています。
また、物流デジタル人材の不足に対しては、シミュレーションによる支援だけでなく、当社内にいるデジタルドリブンな人材が、お客様の社内で常駐するようなサービスも実現できたらと考えています。