工場内物流の自動化と統合によって人口減少時代の製造業の持続可能性を実現
人的資本経営が叫ばれつつも加速する人手不足と人材の流動化。我が国の製造業においては属人的な工場内物流が課題となっています。そうした背景のもと、E80グループジャパン合同会社は、イタリア発の革新的な物流自動化システムで新たな可能性を提案しています。日本法人設立の経緯から、デジタルネイティブ時代の物流の未来像まで、E80グループジャパン合同会社 竹山 康宏氏(ゼネラルマネージャー)にお話を伺いました。

E80グループジャパン合同会社
イタリアに本拠を置くE80グループの日本法人として2022年に設立。同グループはLGV(Laser Guided Vehicle:自動搬送リフト)を軸とした搬送自動化システムをグローバルに展開する。工場内のモノの移動だけでなく、ソフトウェアによって統合された自動化システムのソリューション提供が特徴。
ゼネラルマネージャー 竹山 康宏 氏 Yasuhiro Takeyama
1999年神戸大学工学部情報知能工学科卒業。神戸大学大学院自然科学研究科で情報知能工学を専攻し、冗長自由度を活用した2次元ロボットアームの振動軽減の研究を行う。機械系の専門商社で営業職に従事後、ボンド大学にてMBAを取得。2022年にE80グループジャパン合同会社を設立し、ゼネラルマネージャーに就任。
先進的な自動化のビジョンに共感し日本法人を設立
――E80グループについてご紹介ください。
当グループは、1992年にイタリアで設立された、工場内の物流自動化を実現するソフトウェアや自動化機器を提供するグローバル企業です。飲料や食品、家庭紙製造の工場を中心に、LGV(Laser Guided Vehicle:自動搬送リフト)や工場全体の物流自動化を統合するソリューションを提供しています。
昨今では製造工場に限らず物流センターにも自動ピッキングを含めて完全自動化システムの提供を行っています。
創業者であり現社長のEnrico Grassi(エンリコ・グラッシ)は、創業時から「これからは、マーケットから工場までシームレスにつながった工場運営が不可欠である」とのビジョンを持っていました。そのうえで、製造業におけるIT技術の導入や改革を目指すインダストリー4.0(第4次産業革命)のコンセプトを先取りして、工場内物流の自動化に取り組んできました。
――市場への取り組みについて教えてください。
E80グループの主要市場は北米ですが、欧州各国、南米、オセアニア、アジアの企業にも多くの導入実績があります。現在では世界の約450の工場で9,000台以上のLGVの導入実績があります。特に食品・飲料製造業界から高い評価をいただいています。
――日本法人を設立した経緯にはどのような背景があったのでしょうか。
日本の拠点となるE80グループジャパン合同会社は、2022年に設立された世界で14番目の拠点です。設立の背景にはイタリア本社の日本進出の思いと、私自身の思いが重なったことがあります。
前職の機械商社に勤務時代に、E80グループの製品を扱っていました。2021年までに2件のE80の製品導入の大型プロジェクトに関わった後、国内においてもしっかりとしたサポートを続ける必要性と責任を感じていました。同時に、E80グループでは魅力的な製品を扱っているにもかかわらず、その魅力がまだまだ日本市場には十分に伝わっていないといった課題も感じていました。そこで、2021年に前職を退職し2022年9月に日本法人を設立することに至ったのです。
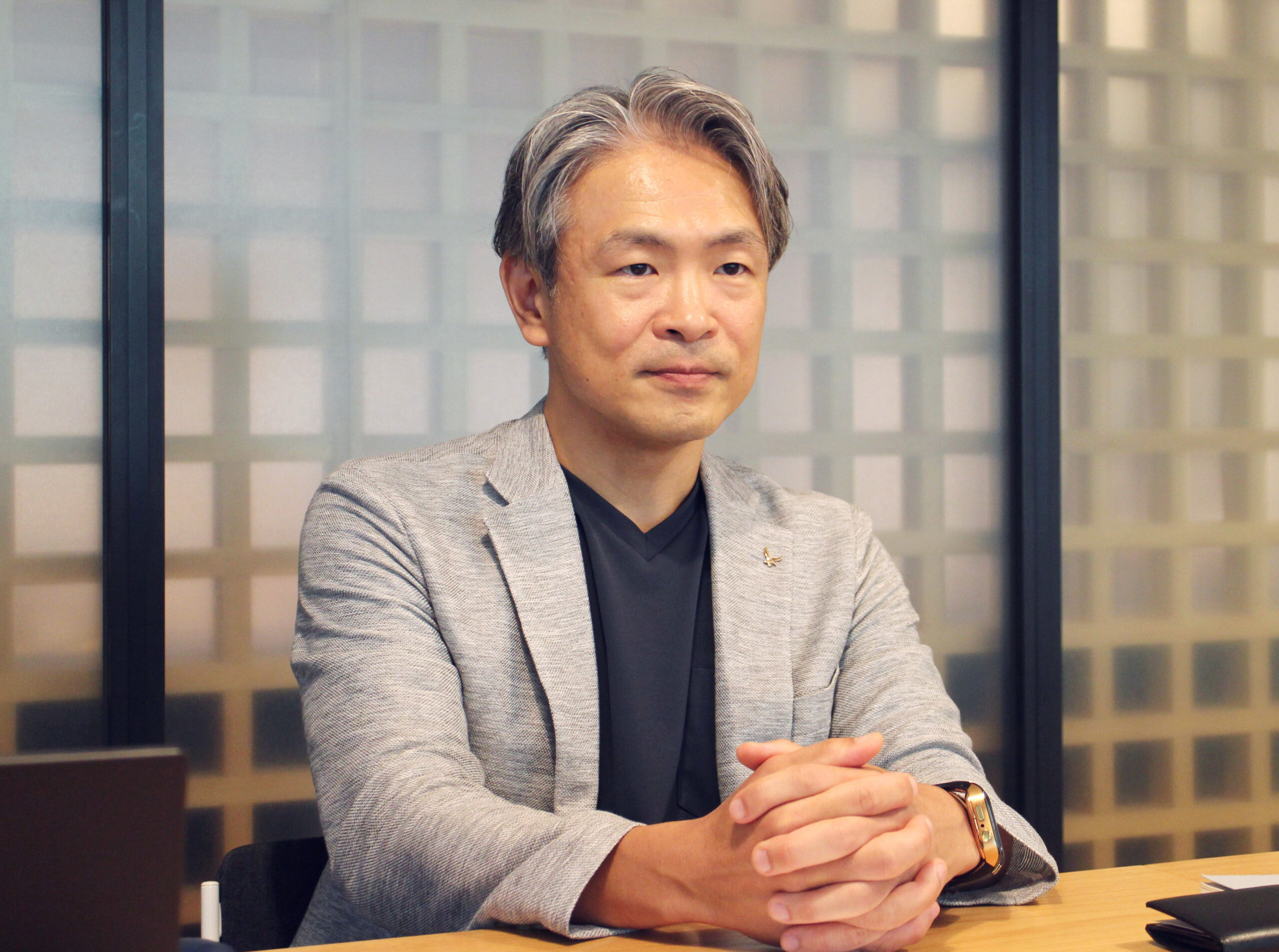
日本の物流が直面する課題は人材に起因する
――日本の物流・ロジスティクス市場における課題について教えてください。
日本法人を設立後、多くの日本企業の方々とお会いするなかで、4つの課題があると感じています。
まず1つ目が人材採用です。少子高齢化が加速し、15~64歳の生産年齢人口は2025年の7,170万人から2065年には4,529万人まで減少するとされています。2025年から約36.8%も減少するのです。2025年時点の東京都の人口1,425万人と大阪府877万人の合計以上の2,641万人もの担い手が減少するとされるなか、足元においても人材採用の課題は深刻化しています。
例えば首都圏の物流拠点においては、人材の取り合いによって採用コストが上昇しています。そもそもその地域に住む人たちが限られるなか、採用できる人数にも限りがあります。また、人材がより好条件や高い時給へ移動する流動化や、24時間操業の夜間シフトの人材確保がより深刻化しています。
2つ目が人材の定着率の低下です。採用後もより良い条件の職場に流れてしまうため、何度採用し教育しても辞めてしまうという悪循環に陥っています。そのため製造や物流のオペレーションの品質が安定せず、ミスやトラブルの発生が頻発します。
――人材の採用と定着は大きな課題ですね。
おっしゃる通りです。これらに起因するのが、3つ目の課題です。ナレッジトランスファーの断絶、いわゆる知見や技術の継承が途絶えてしまうことです。人材が辞めてしまうことで、できていたことが不可能となってしまうのです。高齢化した熟練オペレーターのノウハウや経験が継承されずに安定稼働のリスクになっているケースもあります。
外国人労働者の導入もすぐには解決策にはならないと考えています。多言語対応や品質管理の課題も加わり、単なる人の置き換えでは解決できない複合的な問題となっています。
最後に4つ目は、部分最適の弊害です。現場に最適化された仕組みも全体最適の視点ではボトルネックになることがあります。部分最適のつなぎを人が担う属人化したオペレーションが全体最適を阻害しているケースがあります。
ハードウェアだけでなくソフトウェアの提供でソリューションプロバイダーを目指す
――それでは御社のソリューションについて教えていただけますか。
先述の課題に対して、E80グループでは(既存の自動化機器メーカーとは)根本的に異なるアプローチを提案しています。私たちはハードウェアを提供しているサプライヤーとしてではなく、ソリューションプロバイダーとして、全体最適の課題解決に貢献しています。最大の特徴は、LGV単体の提供だけではなく工場全体の最適化を実現するソリューションの提供です。具体的には、単なるA地点からB地点への搬送の自動化ではなく、倉庫管理などの前後の工程まで含めた対応を行っています。当社では搬送、倉庫管理、パレタイズや入出庫までを自動化し1つのシステムとして統合することが可能です。こうした自動化によって、人件費の削減だけでなく、より短時間でより多くの製品を製造できる生産性向上を実現しています。
具体的な事例が、イタリアのパスタメーカー・バリラの工場です。生産ラインが26あるこの大規模な工場では、約110人のフォークリフトのオペレーターが工場内の資材や製品の搬送を担っていました。現在ではこうした搬送工程をすべてLGVに置き換えることで、たった2人で工場内の物流を管理しています。タブレット端末を下げたスーパーバイザーが自転車で構内を巡回しながら、LGVの動態や進捗状況を把握しています。
E80グループはソフトウェアと自動化機器群により工場内の物流自動化ソリューションを提供
――自動化の進展によってどのような変化が考えられますか。
仕事の内容が変容します。これまでのフォークリフトの運転が、タブレット端末でLGVをモニターする仕事に変わります。また多言語対応によって、日本人、外国人に関わらず、アウトプットの品質が平準化されると思います。人に依存しない自動化と業務の平準化が実現します。
当グループの製品の特徴はソフトウェアにあります。VUCA時代のマーケットの変化に対応するためには、硬直的なハードウェアよりも柔軟なソフトウェアによる対応が重要だと考えています。例えば、コンベヤのような固定的な設備では、フレキシビリティに制限があります。私たちは極力コンベアを減らすためにLGVを活用する提案をしています。LGVはソフトウェアの変更だけでモノやLGVの導線の変更が可能なため、マーケットの変化による物流ニーズにも柔軟に対応できます。
――柔軟な対応が可能ですね。
はい、当グループのLGVの特徴は、お客様の課題に合わせてカスタマイズできることです。例えば、お客様の工場で高さ制限があれば、マストの高さやレーザーの位置の変更が可能です。
日本の物流環境とも近しい欧州の事例や知見を活かしたい
――「ロジスティクス強調月間2025」のサポーターに参画した経緯について教えてください。
日本法人の設立後、当グループのコンセプトを日本のお客様にご理解いただく取り組みを続けています。今回、サポーターに参画した背景には、「人材不足が加速する我が国の工場物流の課題解決に貢献したい」との思いがあります。お客様の課題をしっかり理解しつつ、当社のソリューションをお客様に知っていただきたいと考えています。
E80グループの欧州のお客様は日本市場と似たような環境的な制約があります。土地が広い米国市場では、敷地を広げ新たな自動倉庫を新設することも容易ですが、敷地が限られる欧州では、既存施設の有効活用が必要です。日本においても固定的な自動倉庫や搬送ラインをいったん構築してしまうと、事業環境の変化に対するフレキシビリティーに制約が生じます。既存リソースの有効活用とフレキシビリティーの両立が必要です。
また、当社が提供する製品群は、各社の多種多様なマテハンとの連携も可能なため、日本のお客様の環境に最適な課題解決が可能です。単なる部分最適のハードウェアの提供ではなく、全体最適を目指す新しいアプローチができると考えています。
ロジスティクスの未来に向けた取り組み
――E80グループが描く物流の未来像はどのようなものでしょうか。
グローバルのE80グループが描く物流の未来像の1つに「フォークリフトのオペレーターがゼロになる」ということがあります。今後の自動化の進展によって、10年後のフォークリフトのオペレーターは約8割は減少するのではないでしょうか。こうした変化に対応するソリューションをいかに開発し、市場に提供していくかが重要になると考えています。サステナビリティとはシュリンクラップの削減やCO₂の排出削減だけではありません。現在の事業を持続可能とするために「人に頼らない」仕組み作りが必要なのです。
――未来の物流の人材育成についてはいかがでしょうか。
人材育成の考え方が根本的に変わるのではないでしょうか。物流にもITスキルが必須となることは避けられないと思います。デジタルネイティブの世代はスマホをスクロールするように物流のオペレーションを行っていくのではないでしょうか。こうした人材が今後の物流業界を担っていくと考えています。これまで、どちらかというと物流のイメージはネガティブでした。こうした業界イメージも劇的に変化すると考えています。ゲームの世界のように仕事をやりたいと思えるような業界になるのではないでしょうか。
またジェンダーレスも進行し、これまで男性の仕事と思われていた分野でも、女性の活躍する機会が増えています。E80のシステムが導入されたエビアンの工場では、女性のロジスティクスマネージャーが活躍しています。
私たちE80グループジャパンが描く未来は、自動化を超えたより生産的で持続可能な工場運営へのゲームチェンジだと考えています。日本のお客様と一緒に、新しい未来を実現していきたいと思っています。
